子どもが成長するにつれて増えていくものの筆頭は家族の食費。
特に一人親家庭では、削りたくても削れない固定費のひとつです。
これから子どもが小学生から中学生、高校生、そして大学生へと育っていく中、
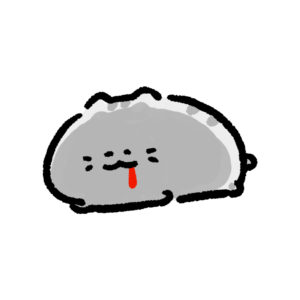
「どのくらい食費がかかるのか…」

「どんな工夫でやりくりできるのかしら」
と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、実際に子どもを小学生から大学生まで育てたシングルマザーの私が、各ステージごとの食費の実態と、その中で工夫してきたことをお伝えします。
最後まで読んでいただくことで、なんとかなった成功例から、ほんの少し安心感が得られるのではないかと思います。
子どもが小学生の頃の食費〜まとめ買いと基本自炊でやりくり
小学校時代の我が家の食費は、月々およそ3万円。
週に一度のまとめ買いで、1回あたり7,000円〜8,000円ほど使っていました。
この頃は、子どもたちは週のうち2日はパパの家で過ごす、という生活習慣だったのでその分の食費も浮いていたこともあります。
学校が休みの土日は、お金がかからないアスレチックや公園にお弁当を持って遊びに行く、ということがほとんど。
ひと休みにカフェに入ったり、疲れたから夕飯はファミレスでということもなくとにかく自炊!で乗り切っていました。
疲れていても自炊する覚悟を決めたことが、早くに「自炊する習慣」がついたのだと思います。
どんな状態でも基本は自炊中心。冷凍食品や惣菜は割高になるためあまり頼らず。
栄養バランスに関しては、意識しているというよりも、野菜は必ず食卓に出す!というスタンスで気楽に。
買い物のルールは、お肉は100グラム100円以下のもの、野菜は100円以内なら買う。
子どもたちは、買い物に来たがらなかったので、仕事終わりの買い物はなし。
広告の品やポイントを求めてスーパーをハシゴなどは時間がもったいないと感じ、あったらラッキー程度という温度感です。
このころは、あまりお魚は食卓に出さなかったような気がします。コストパフォーマンスと子どもの食いつき方によりお肉中心。
お菓子に関しては、子どものリクエストを聞いてファミリーパックを買ったり、時々ちょっと変わったお菓子を選んだりしました。
外食はコンビニ食は1年に1〜2度という程度。とにかく自炊で乗り切ることを徹底していました。
中学生になると食べ盛りが本格化!増える量と孤食対策
中学生になると、食べ盛りが本格化。
食費は月々約4万5千円に増加しました。
土日は部活動になり、毎週のお弁当が必須。
この時期から買い物スタイルも少し変化。まとめ買いに加え、牛乳や日配品などを買い足す機会も増えてきました。
子どもたちの部活や所属していたスポーツでの遠征に保護者の送迎が必要だったため、家で留守番をする子は孤食になる割合が増えてきました。
また、子どもたちがそれぞれの時間で帰宅することが増え、家族で食べる時間が減ったな〜と感じ始めたのもこの頃です。
私はできるだけ子どもが一人で食事をとることがないようにと決めました。残業が発生しないように働き方を調整したり、それが難しければ転職。
仕事で遅くなると分かっている日は朝のうちに夕飯を作ってから、二人で食べてねと手紙を置いたりして出勤したりしました。
食費だけでなく、生活スタイル全体の工夫が必要な時期です。
高校生の弁当生活と買い物スタイルの変化
高校時代の食費は月々約5万円強に。
毎日お弁当を作る生活が始まりました。
トータル5年間にわたる毎日のお弁当生活でお弁当を作れなかった日は片手で数えられるほど。
お弁当作りも朝のルーティンに組み込めば「習慣化」することも難しくはありませんでした。
買い物スタイルにも変化が。
娘は厳しい部活動に所属していました。
この頃になると、娘の部活動での送迎がかなり遠くまでの遠征となり土日でも買い物が行けません。
ですが、コロナの影響で部活動も停止。私の仕事も在宅勤務になったこともあり、買い物スタイルは自然と日常の隙間時間を見つけて日々必要なものを買い足すスタイルにシフト。
二人とも進学コースに所属していたので、それなりに早い時期から、受験対策の勉強生活始まりました。
これまで通り、菓子パンなどの割高な商品は避けて、主に食パンやバターロールを甘くしたりサンドウィッチにしたりして活用していました。
相変わらず外食やコンビニには頼らず、毎日自炊。
料理が得意ではなかった私でも、簡単でおいしく、量が確保できるメニューを工夫して作るようになりました。
大学生と同居でも食費は増加|大人の味覚と遠慮のなさが影響
大学時代になると、子どもたちは自宅から通学しており、家にいる時間が再び長くなりました。食費は月々およそ6万5千円に。
高校時代までの子どもたちの食事は、出されるがままの食生活でした。
二人が通う高校が、規律の厳しかったこともあり、友達と外で食べるということもほとんどありませんでした。
が、大学生になると大人の味覚に近づきます。加えて、外で食べることも増え、アルバイト代で好きなものを食べれるということで舌が肥えてきました。
コーヒーやチーズ、ナッツ類など、割高な嗜好品のリクエスト割合が一気に増加。
また、子どもたちは一人暮らし経験がないためか、食に対する遠慮がなく「あるものを遠慮なく食べる」スタイルに拍車がかかります。
家族全員の好みが肉から魚へシフトしたこともあり、少しコストがかかり気味な魚が食卓に出ることがぐんと増えました。
買い物スタイルに関しても、子どもたちが大きくなったことで買い物に行く時間が夜遅くても問題なくなりました。
見切り品の購入機会も増えたこともあり、魚料理の割合も増加。疲れて「今日はお惣菜フィーバー!」の日も。
お昼は自分たちで(子どもはアルバイト代などから)用意というルールにしていますが、家での朝食や夕食はしっかり食べるので、やはり負担は大きくなります。
それでも、自炊である程度コントロールできること、そして「家で食べてくれる」ことの安心感は大きなものです。
あと何回、一緒に食卓囲めるか、そういうフェーズに入っていますね。
食費は確かに増える、でも自炊を習慣化すれば乗り越えられる
子どもが成長するにつれて、家計にのしかかってくる食費。
でも、歯磨きやお風呂を毎日入るように、疲れている時でも自炊が習慣化していれば「えいやっ」と体は動きます。
つい先日、息子とも話していてびっくりしたのが、「この11年間、私たちで外食したのって1回…だけ?」ということ。
確かにしんどいと感じる時期もありましたが、「食卓は生活の満足度を上げる時間」ととらえて、自分の自炊の負担を減らす工夫をしつつも、節約しすぎないことを意識してきました。
毎日の自炊は大変です。が、その分、子どもたちの健康面をサポートできた安心感があります。
そして子どもたちから「あの料理が食べたい!」と言ってくれる機会が増えることは、心の中ではガッツポーズものです。
家族でワイワイしながらの食事の時間はかけがえのないものです。
それに料理下手な私の失敗料理は、子どもたちとの笑いのきっかけにもなりますし、それを「#失敗料理」として Instagramにもネタとしてアップしていました。(楽しむこと大事!)
子供が大学生になると、みんなで食卓を囲む機会も減ってきます。
今振り返ると、小中高の頃に一緒に食べたごはんの時間は、忙しい毎日の中でもとても大切な思い出です。
私は料理上手ではありませんが、限られた予算の中で工夫と気合いでなんとかやってこれました。これから子どもが成長していく中で、食費のことで悩んでいる方にとって、少しでも「やっていけそう」と思っていただけたら嬉しいです。
それではまとめいきましょう
シングルマザーの家庭において、食費は避けて通れない大きな出費です。
しかし、子どもの成長ステージに合わせて柔軟に対応することで、ムリなくやりくりすることができます。
そして、早いうちから自炊を「習慣化」することが良い結果をもたらします。
「栄養」「満足感」「節約」この3つのバランスをとりながら、家族との時間も大切にしていく。
そんな日々の積み重ねが、やがて家族のかけがえのない記憶になっています。
